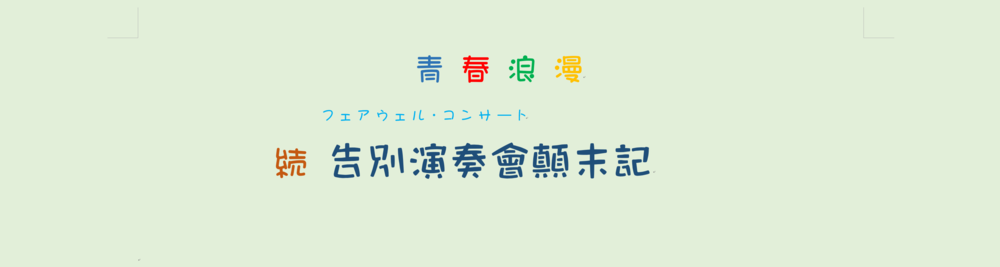
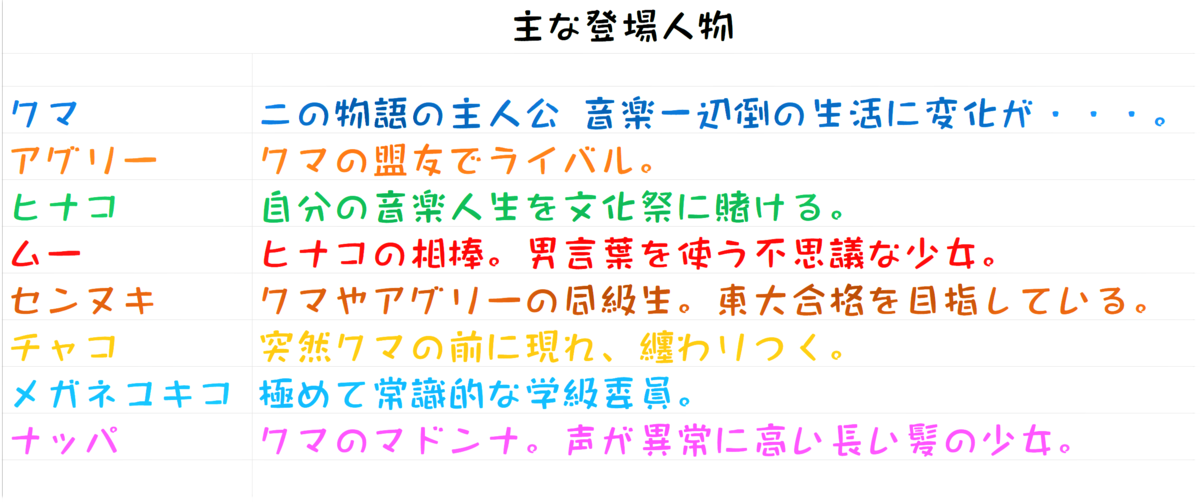
「変わってないな」 6年前、10日余りの間閉じ込められていた建物を、久し振りに眺めクマはそう呟いた。正面玄関から中に入ると、ひんやりとした微かに消毒液の臭いの漂う空気が彼の遠い記憶を呼び覚ます。
過ぎ去った歳月は決して短くはない。しかし誰にでも何年経とうと決して忘れない思い出はある。たとえそれが単なる「入院」であったとしても、それ迄の十二年の人生で初めての経験となればある意味当然とも言えた。
そしてクマはまた、瞑想にも似た思考の迷路に沈み込んで行った。
『自分は幼い頃から喉が弱かった。風邪を引き易く決まって扁桃腺が腫れ、咳が止まらなくなる。そして四十度近い高熱。眠っているのか起きているのか、夢か現か、或いは生と死の間か。そのような状態が三日三晩続き漸く快方に向う。それがいつものパターンだった。しかし、あの時は違った。
「肺に白い影が見えますね、ラッセルも酷くなっている。国立第二病院に紹介状を書きましょう」レントゲン写真を見せながら医者が母親にそう告げた。ラッセル、それは一体何なのか。線路上に降り積もった雪を強靭なプロペラで吹き飛ばす黒い機関車みたいな、いや違う、あれは確かロータリー車だ。ラッセル車は、そう、アイロンのお化けみたいな形をしたヤツ』
確かに彼はそうやって自由連想のように思考を発展させてゆく事が好きだった。しかし、その過程で生じた疑問を如何にして解消するか。まだ小学生だった頃、多くの子供達が置かれた環境は、彼等の好奇心を全て満たす程整ってはおらず、彼等自身もまた理解力に欠けていた。
ラッセルの正体が不明のまま、国立病院での診察の結果、彼は即日入院治療となった。
『聞けばよかったのだ。それを答えられる誰かに』出来得る限り自分自身で物事を解決したいと考えるクマは、やがて人にものを訪ねる事が最も安易で且つ確実そうな方策である事に気づいた。
『そう、ラッセルにしても、入院中ペニシリンを腕に打つという疑問も、その場で医者に聞けば、多分小学生にも分かり易く説明してくれた筈だ。それをしないまま放置してしまった。今ここで心に刺さったままの棘のような懸案事項を解決しなければならない。長く閉じこもって来た殻を自らの手で破壊出来る事を証明をする必要があるのだ』
そして彼は、ふと傍らにいるチャコに気づく。
『まずいな、また嫌味を言われるかも知れない。僕は別に異次元にいる訳じゃない』
「構わないわよ」チャコがクマの心の動きを見透かしたように上目遣いで言った。
「私、先生の居場所を聞いてくるわ」そして彼女は総合受付の方に向かって歩き始める。
「ああ。僕も一緒に行くよ。ちょっと確認したい事があるんだ」
チャコが受付の年長者らしき女性に司書教諭がいる病棟を確認している間、クマはそのとなりに座っているひっつめ髪の若い女性に訊ねた。
「あのう、ちょっとお尋ねしますが」
「はい、何でしょうか」彼女は顔を上げた。
「この病院を国立第二病院と言うのは何故ですか」クマは少し照れ臭そうに言う。
受付嬢は一瞬眉をひそめ怪訝そうな顔をしたが直ぐに笑顔を作り、そして答えた。「新宿に国立第一病院がありますが、それは知っていますか」
「いいえ、でも第二がある以上、第一があるのが普通ですよね」
「そうですね。でもそれだけではなくて、ここは昔は、海軍軍医学校第二付属病院と言ったそうです。新宿の第一病院は元は陸軍病院だったので全く違う組織。ただ、第一付属病院があったのかどうか。それ以上のことは私も判りません」
「そうですか、ふうん、そんな話があるんですね」クマは目を大きく広げ二三度頷いた。
実際のところ彼は非常に満足していた。得られた情報はごく僅かではあったが、それをとても貴重な宝石のように感じた。
『何しろ、自分から知らない相手に話しかけた事が評価できる。これで、帝国陸軍と海軍の違いを調べれば、結構面白いレポートが書けるかも知れない』彼が太平洋戦争について知っている事は決して多くはなかった。『今ならまだ生き証人が沢山いるし』
「また何か考えていた」チャコはピーナッツコミックの登場人物が相手をからかう時のように違う方向に目をやって言った。
「どこだか判った」彼は苦笑しながらチャコに聞く。
「それが、一昨日退院したんですって」
「えっ、それは治ったって事」クマは確認するかのようにゆっくりと発音した。
「ううん、そうじゃないみたいだけど、詳しい事は判らないので家に帰って母に聞いてみます。ごめんなさい、ちゃんと調べておけば良かった」
「いや、全然。気にすることなんか無いよ」
「これからどうする」
「そう、家に帰ろうかな、色々ほったらかしにしている事もあるし」
「うん、先生の事何か分かったら連絡します。今日はありがとう」
「いいえ」クマは精一杯の笑顔をチャコに向け、そしてギターを弾くような手つきをしながら言った。
「それと僕はそろそろ、こっちの方に戻らなきゃ」
