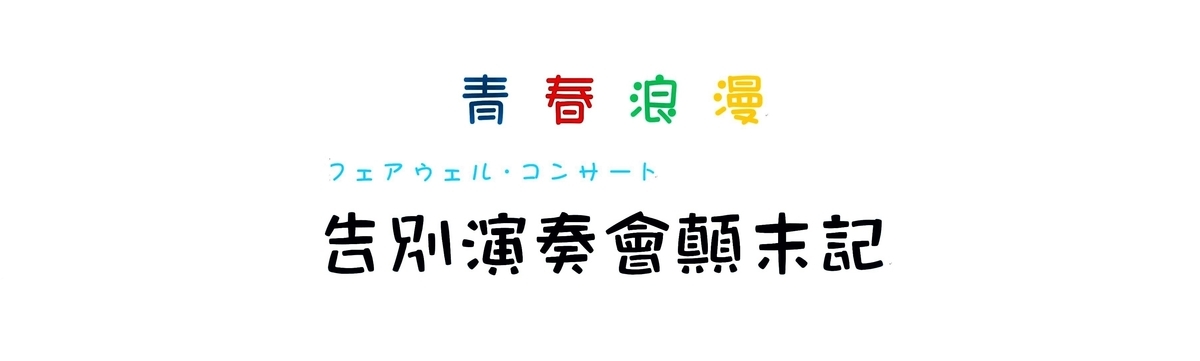
2.「僕達は週刊DANDYを発行します」編集部一同が宣言した (1)
年が明けて1974年1月、その機能的外観から「軍艦島」と呼ばれた三菱端島炭鉱閉山のニュースが巷に流れていた。 それとは全く何の関係も無く、深沢全共闘、兼新聞委員のアガタの発案のもと週に1度、2年4組内に限って機関誌を制作、発行する運びとなった。
全共闘とは言っても、所謂学生運動のピークは既に過ぎており、学内にその流れを汲む3年生が数名いて、ヘルメットにタオルの覆面というお約束の装束に身を包み、入学式等に出没してはビラを配ったりする他は、特に目立った活動はなかった。そしてその連中の拠点が新聞委員会の部屋だった。
因みに、校則では一応制服を定めていたが、生徒の大半は着用せず、主流はVANやKENTに代表されるアイビールック。それ以外の者はパンタロン(当時ベルボトムという言い方はしなかった)のGパンに長髪というスタイルで登校していた。この『私服黙認』、これ位がかっての運動で勝ち取ったものの名残と言えるかも知れない。
さてこの機関誌は「DANDY」と命名され、編集は発起人で顔に迫力がある割には意外に軟弱なアガタ。尚、彼はその容姿をかわれて、足尾鉱毒事件の田中正造を扱った三國連太郎主演映画「襤褸の旗」にエキストラの一人として出演した実績があった。服装は上下ともジーンズで、いつも流行りのマジソン・バッグを持ち歩き「欧陽菲菲のボディーラインは抜群だ」と言っては手のひらで顎を撫でながら、涎をすする音を出すのが趣味だった。
編集局のもう一人は1年生の3学期、他所の私立男子校から編入して来て、いきなりクマ達が噂でしか聞いた事がなかった「バレンタイン・チョコレート」とやらを貰った実績があり、そして機関紙名にもなったダンディー。彼はバレーボールが得意なスポーツマンだが、編入の理由は何故か誰も知らなかった。
あとは此の手の話には常に顔を出すセンヌキとクマ。その4人でスタートし、後にアグリーやトシキ、カメといった「深沢うたたね団」の面々も加わった。
この機関誌は思ったより不評で彼等を落胆させたが、特にアガタはアグリーが入った為、「紙面がハイプになった」と一時編集局を去ってしまったりした。彼にしてみればこの機関紙発行が2年4組との決別の辞であり、ある意味フェアウェル・コンサートだったのかも知れない。
因みに、ハイプとは本来ニセモノという意味だが、彼等は『ダサイ、クサイ、カッコ悪い』等を総称する言葉として使っていた。尚、その反意語はヒップである。
アガタは一応立場上、反体制的でアナーキーぽい記事を担当し、センヌキはそれを軟弱に追従する文章を書き、クマは当然ナッパの事しか頭にないので、詩ともエッセイともつかない、何かを語っているようで実際は何も言っていない、要は意味不明なコラム「深沢うたたね団の伝説」を担当した。例えばこうである。
朽ちかけた長い回廊を抜けた時、
早春の陽光は眩しく暖かかった。
透き通った新緑の若葉が風にささめくのを聞き、
僕はまた新しい詩を一つ書こうと思った。
汚れなく白い思い出をその言葉に託して、
輝くこのひと時を飾ってみよう。
描きかけのカンバスに絵具を重ねて、
いつかは別れてゆく二人の後ろ姿を見送るように、
栞をさした頁を開いて泪の跡を辿る。
流れ星が燃え尽きたら僕は広い夜空の何処かに、
願い事の一つを失くしたように
星々の間を探すけれど、
心の中で歌はいつも独りぼっちだった。
遠い夢の旅路をさすらう人の、
あの優しい微笑みにもう一度出会えたら、
白百合の花に包まれたイースターの街に
夜明けを求めて、
さあ行こうワトソン君、
ガニマールでは頼りにならないからね。
編集後記担当のダンディーは「最初ハイプかと思ったけど、最後はヒップで締めたね。」と評してくれたが、クマはナッパがこれを読んで、クスッとでも笑ってくれたのなら、それだけで満足だと思っていた。 <続>
ここ二回、アグリーの作品が続いたので、今回はクマの意味不明な文章に連動して「イースター・リリー」 という曲を。
